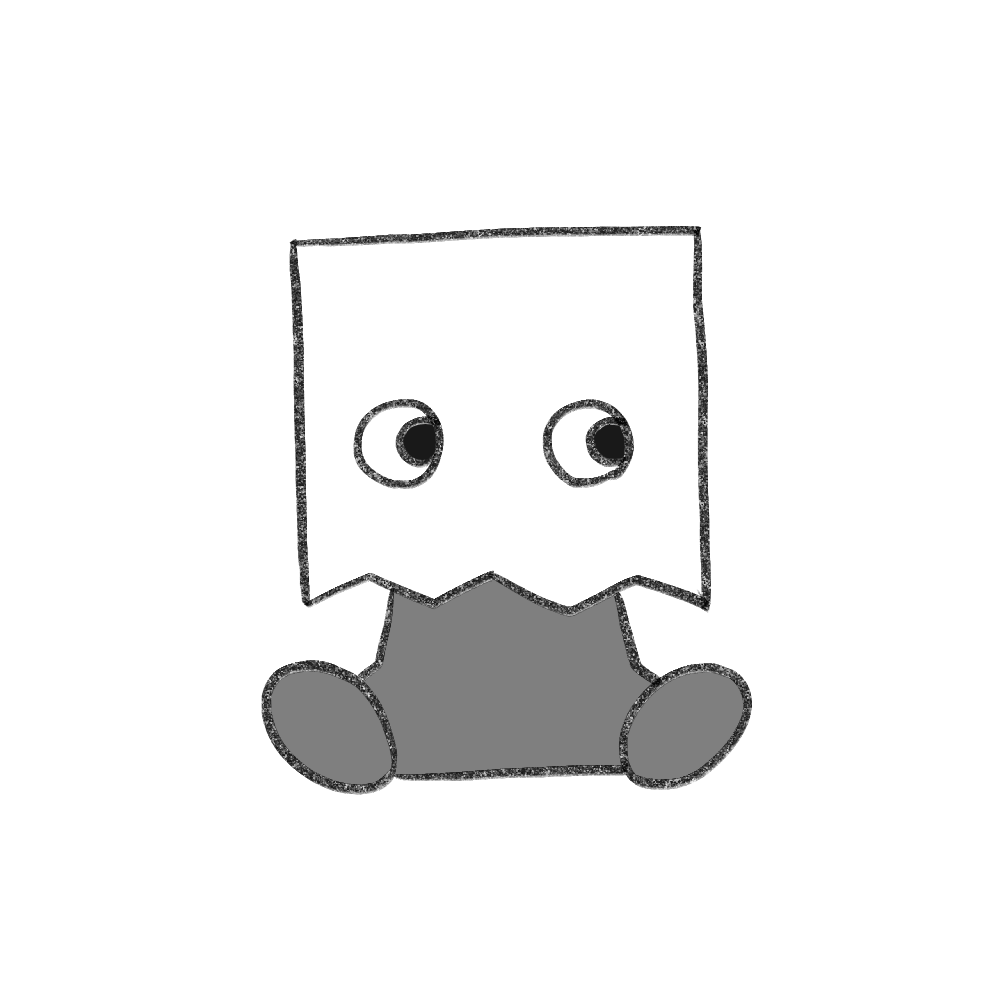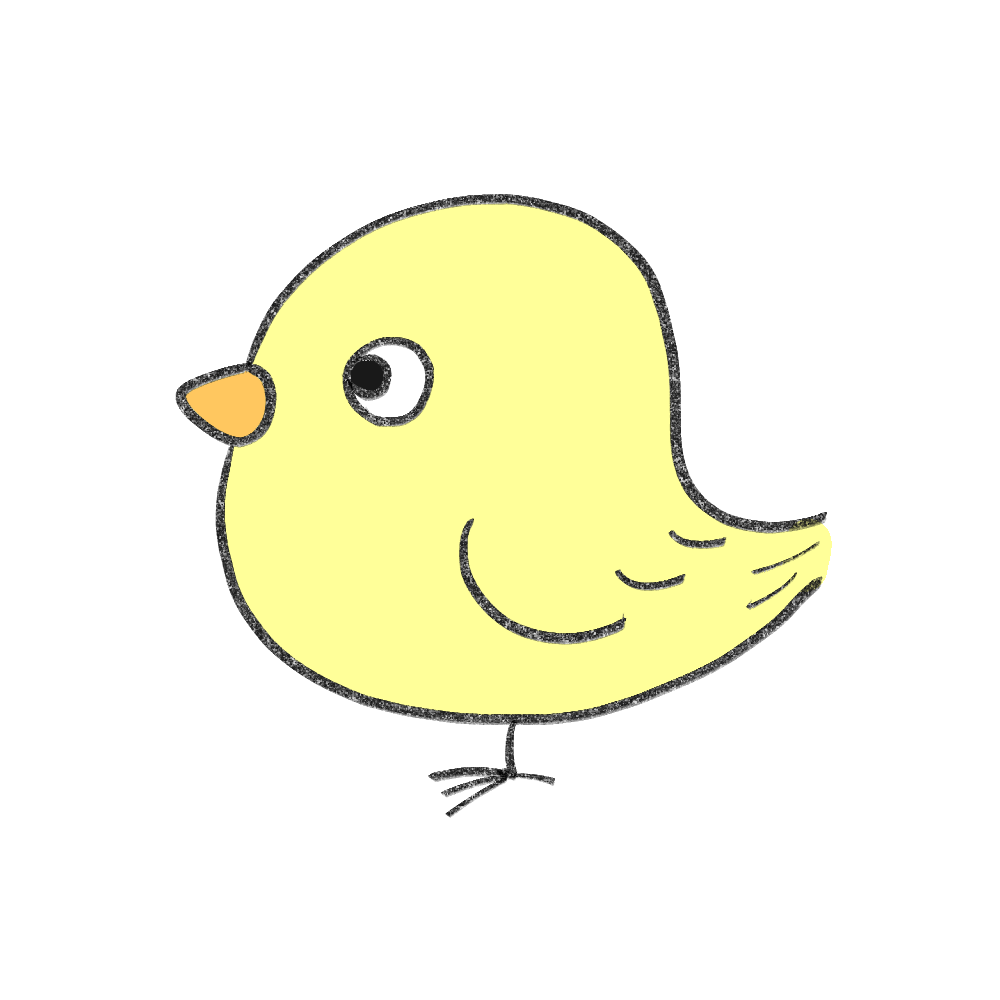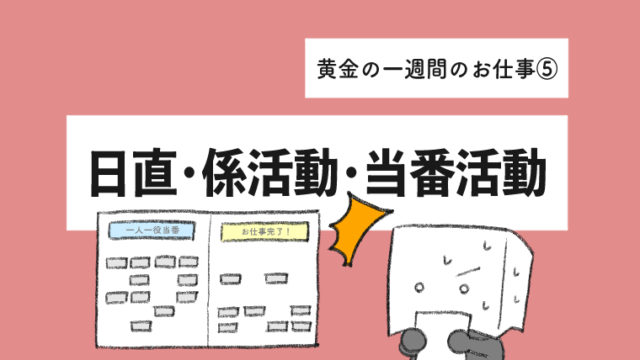
\黄金の一週間④はこちら/
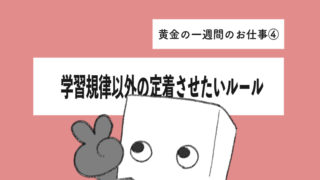
Contents
📕係活動や当番活動では、チェック表を作るべし!

教員になって思ったこと。子どもって忘れやすいし、楽な方に流されやすい!
例えば夏休み、「毎日朝と夕方に靴並べのお手伝いをする」という宿題があったとして…
自分でそれを覚えていてこなす子どもはどれくらいいるでしょうか。
「あっ!忘れてた!」と気づいたものの…
「お母さん気づいてないし、靴並べ面倒だし、いいか〜」
私にもこういうことがありました……(^^;)
学級でも同じようなことが起こります。
「あっ。今日日直で、◯◯しないといけないのに忘れてた」と…。
「あっ。宿題をチェックする係の担当日なのに、忘れてた」と…。
そう。子どもによっては、大人がチェックしないと行動するのが難しいことがあります。
大切なのは、子どもの「やり忘れ」をそのままにしないことです!
子どもの「やり忘れ」を見逃さないために
子どもの「やり忘れ」を見逃さないためのオススメの方法は、チェック表を作ることです!
例えば、先程の夏休みの靴並べの場合、「朝靴並べをしたらチェックをつける。夕方も靴並べをしたらチェックする」という紙を準備すると、忘れることが少なくなりますよね。
さらに、そのシートを他の人からも見られる場所に貼っておくとどうでしょう。
親はお手伝いをしたかどうか、一目でわかるようになりますよね。
さらに、表を見た家族が「何か忘れていない?」と声をかけるかもしれません。
子どもはお手伝いを忘れにくく、さらに親も管理しやすくなって、一石二鳥です。
教室でも同じです。
チェック表を作ることで、いちいち指示しなくても自分で動くことができるようになる子どもが増えます。何より、担任の先生が楽になります。
日直について
日直の仕事は、最低限でこれくらいあります。↓
- 朝の会
- 朝自習
- 午前中(1〜4時間目)のあいさつ
- いただきます
- ごちそうさま
- 午後(5〜6時間目)のあいさつ
- 帰りの会
自分で自分を管理するために…
このような表をつくります。そして、仕事をし終わったらその都度マグネットを右側のオレンジゾーンへ移動させるようにします。↓

朝自習の際には、「◯◯さん、ちゃんとしてください」と日直に注意をさせます。
このとき、「日直以外の子が注意をするとうるさくなってしまうので、日直以外は朝自習に集中すること」と伝えておくといいです。
また、「日直は、1日の流れがスムーズに進むよう、注意をします。だから、注意をされたら、素直に従うようにします」とも、伝えておくといいですよ!
他の人からチェックを受ける場面の設定
下の画像(↓)のように、前面黒板の横あたり(オレンジ部分)に設置するといいです。

徹底させるために
必ず徹底させるために、担任の先生は最初の時期(1周間目〜4月いっぱい)は仕事をしたら必ずマグネットを移動させるよう、日直の動きを見ておきます。
何もしないと、マグネットを動かさない子どもが出てくるからです。
習慣化させるためには、教員の監視が必要です。きついですが、頑張りましょう!
また、慣れた後でも、昼休み前と帰りの会がはじまる際には、教員は必ずボードをチェックするようにします。
📕係活動(当番活動)について

係活動と当番は違うものです。
- 係活動…学級を盛り上げるために「工夫する」お仕事のこと
例:新聞係、イラスト係 - 当番活動…学級を回すために「ないと困る」お仕事のこと
例:黒板消し当番、電気当番
マンガに「係活動として当番活動を実施する」と書いていますが、つまり黒板消し係や電気係が作られてもいいよーということです。学級のためにと考えて作ったものならなんでもいいよってことですね。
当番活動は、一人一役。つまり、30人学級の場合、30個、仕事を管理する必要があります。一方で係活動は1つの係に数名が入っています。ですので、5つ係があれば、5つ管理するだけで済みます。
朝のしたくルール(宿題の提出の仕方)によっては、必要な係があります。
例えば、宿題チェック係や印鑑係、配り係。また、給食の記事ではタイム係を紹介しました。
絶対に必要な係は、出てこない場合教員側から伝える必要があるので、調べておきましょう!(^-^)
\朝のしたくルールについての記事はこちら/
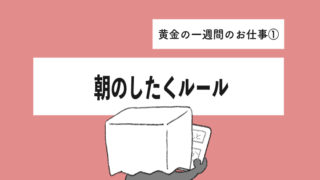
\給食のタイム係についてはこちら/
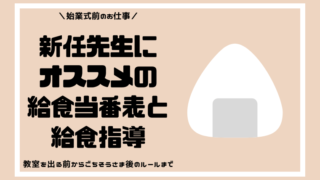
係活動の決め方
こちらについては、わかりやすく説明してださっているサイトをみつけましたので、こちらを読んでみてください↓(2020.4.11)。
教育Zine〜明日の教育を創るウェブマガジン〜,『係活動は「やりたいこと」、当番活動は「すべきこと」』,https://www.meijitosho.co.jp/sp/eduzine/earthleaders/?id=20150023,2020.4.12
また、上のサイトには書かれていませんが、係活動ではいつ(どんなときに)何をするのか、誰が、何曜日に仕事をするのかまで決めることをオススメします。
こちら(↓)の記事では、そのことも考えた係活動の紙の例(pdfデータ有り!)で掲載しています。よければ読んでみてください(^-^)

係活動(当番活動)
係活動(当番活動)も日直のときと同じです。仕事をし終わったらその都度マグネットを右側のオレンジゾーンへ移動させるようにします。↓

他の人からチェックを受ける場面の設定
下の画像(↓)のように、前面黒板の横あたりに日直(オレンジ部分)と一緒に設置するといいです(係は青色)。

必ず徹底させるために
こちらは帰りの会でチェックさせると、係活動がきちっと行ったかどうかがわかりやすくなります。どのようにチェックするのかについては下の記事(↓)に書いています。
\帰りの会についての記事はこちら/
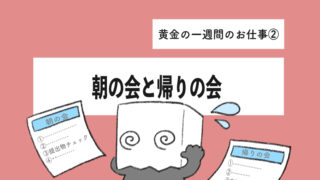
係活動で帰りの会後の窓閉め・机並べが出ない場合は、日直の仕事に加えるといいですよ。帰りの会が終わってさようならをしてから、仕事をして帰るようにさせます。
どうしても一人一役当番をしたい人へ
どうしても一人一役当番をしたい方は、どんな当番があるのか悩むでしょう。一例を紹介しておきます。↓
- 日直と日付書き
- 黒板1時間目
- 黒板2時間目
- 黒板3時間目
- 黒板4時間目
- 黒板5時間目
- 黒板6時間目
- 電気
- 帰りの会後の窓閉め
- 宿題チェック1〜10(出席番号1〜10の宿題をチェックするという意味。詳しくは朝のしたくルールの記事を読んでみてください。朝のしたくルール③で出てきます)
- 宿題チェック11〜20
- 宿題チェック21〜30
- 学習カード印鑑
- 配りお昼休み後
- 配りお昼休み以外
- お花水やり(朝)
…など
教員の「チェックし忘れ」を防ぐために
学級経営のポイントは、指示したことは必ず守らせること(守っていない子どもがそのままにならないようにすること)です。
でも、それがとっても難しい!
まず、これまでに出てきた守らせることはたくさんあります。
これに加えて、さらに大量の業務が加わります。だから「気づいたときにしよう」という意識だと忘れてしまいます。
正直、頭の中に入れられる情報量がキャパオーバーでした。
特に初任者教員は、チェックのルーティンがまだ確立していません。忘れる人が多発します。
だから、まずはルーティンを決めて、紙に書いて持っていてもいいので、一つずつ確実にこなしていくことが必要になってきます。
詳しいルーティンは、こちらの記事に一緒にまとめています↓

PowerPointデータはこちら
\クリックでダウンロード/
参考文献
- 山洋一教育実践原理原則研究論文/全学年/学級経営,『クラスのシステムを確立しよう岡山県津山市立北小学校 岡田健治』,http://www.tvt.ne.jp/~k-okada/g-keiei-kurasu.htm
- 教育Zine〜明日の教育を創るウェブマガジン〜,『係活動は「やりたいこと」、当番活動は「すべきこと」』,https://www.meijitosho.co.jp/sp/eduzine/earthleaders/?id=20150023,2020.4.12
- 『みんなの教育技術,『高学年の学級開きは、荒れ予防のシステムを仕込む!』,https://kyoiku.sho.jp/2067/#i-6
- 子どもたちが進んで活動する当番・係のシステム『2当番活動を機能させるシステム』,http://www015.upp.so-net.ne.jp/tsutsumi/index.html
- EDUPEDIA『1日に自動全員と会話のできる「一人一役当番表」(長谷川隼土先生)』,https://edupedia.jp/article/53233f96059b682d585b65cd