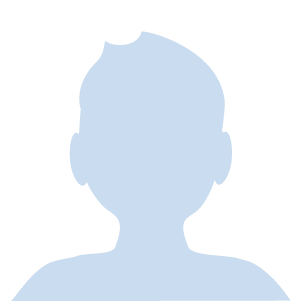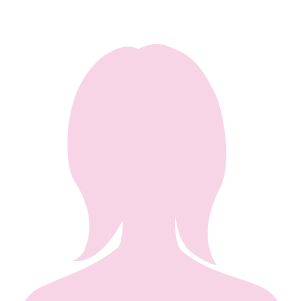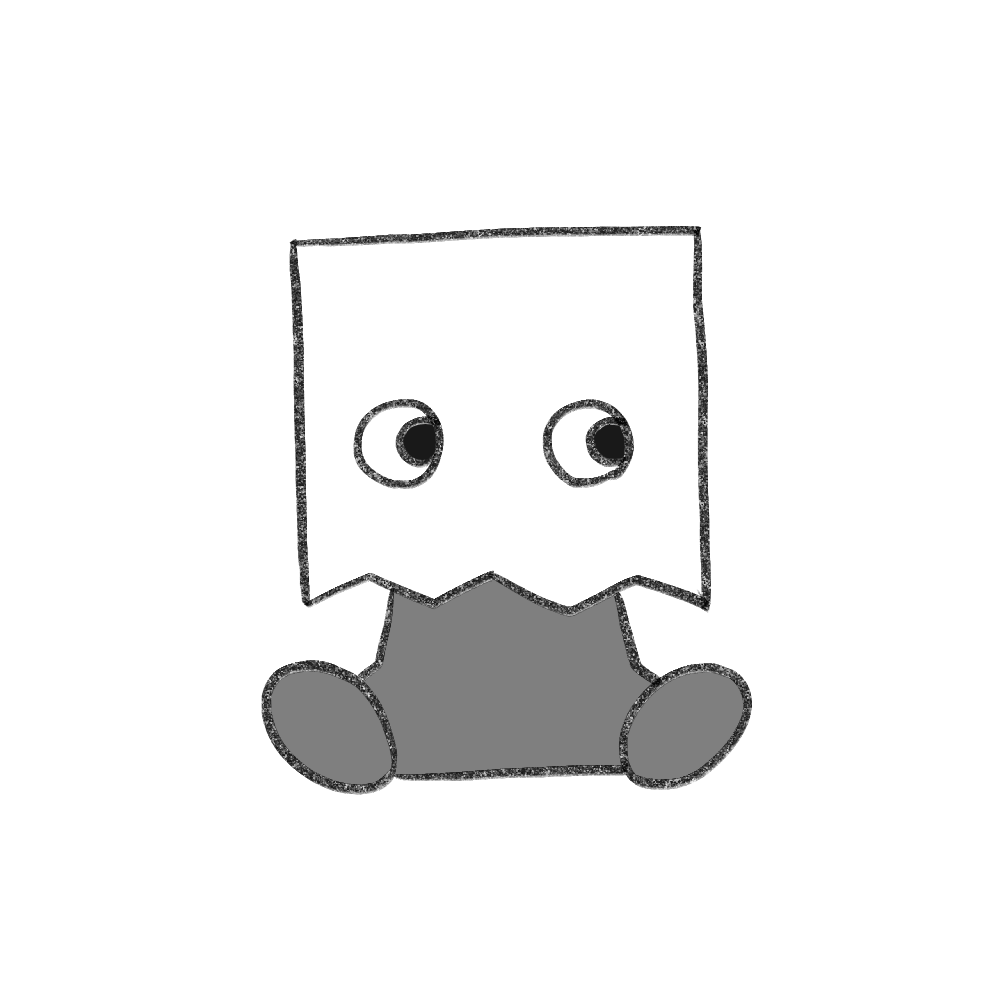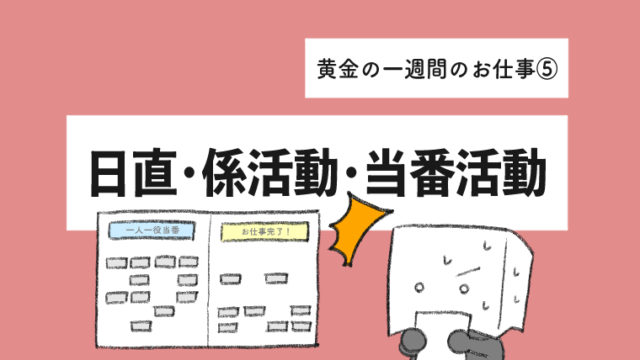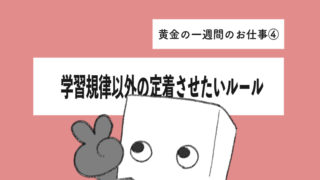\黄金の一週間②はこちら/
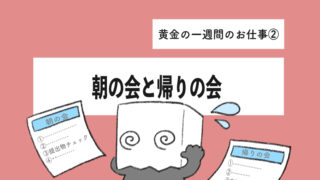
Contents
初任者は学習規律は大切だと知っている。だけど📕

学習規律が大切ってことは、大学で勉強して知っている初任者教員が多いですよね。
でも、学習規律の内容を知っている初任者教員はものすごく少ないんだなと、感じました。
なぜなら、学習規律の内容について詳しく知る機会が準備されていないからです。初任者研修では扱われませんでした。びっくり!

だから、初任者教員は4月にベテラン教員に相談します。でも、そもそも教えてもらえる時間がほとんどありません。ベテラン教員は、たくさん仕事をこなしているからです。
さらに、学習規律ってベテラン教員にとっては当たり前すぎて、「これはわざわざ教えた方がいいことだ」と思わない場合もあります。
結果、初任者教員は、はっきりとした「こうしたらいいんだ」という考えを持つことができないまま、自分の過去の経験(例えば自分が学生だった頃のことや、実習先)を元になんとなくやってみる状態に陥ります。
もう指導力があるないって話ではありません。
運です。運。
たまたまなんとなくやってみた指導がうまくいった初任者教員と、そうではない初任者教員に分かれるんです。
学習規律って?
学習規律は、集団で学習をするためのルールやマナーのことです。
大人の場合、なんとなく「この場でこういう行動をとるのは良くない」という線引を持って、行動することができます。例えば大学の講義で、教授の話を遮って自分の話をする人はいませんよね。周りの人の迷惑になるとわかっているからです。
でも子どもはそうはいきません。
こういうところから、教えていく必要があります。
学習規律の内容
では具体的に、どういうことを教えたらいいのでしょうか?
初任者教員は、もう周りが大人だらけの生活に慣れているので、そこがわかりません。
授業中の学習規律では、このようなことを徹底させます。
- 話の聞き方
- 発表の仕方
- 指示には素早く従わせること
これをさらに詳しくしたものが、こちらです。↓
- 机の上や中は必要なものだけ!
- 筆箱の中身も必要なものだけ!
- 手を挙げて当たった人だけが発表します。
- 手を上げるときには、何も言いません。当たってから「はい」と言います。
- 反応は同じときには「同じです」、そうじゃないときには「わかりました」と言います。
- 友達が傷つくような言葉は使いません。
- お話は最後まで聞きます。話の途中で口は出しません。友達が発表するときも同じです。
- 一生懸命発表しているので、一生懸命聞きます。
- 授業中は、立ち回りません。質問がある場合も同じです。自分の席で、手を挙げて待ちます。
始業式後のはじめての授業のとき(国語や算数でなくてもかまいません。学活のときでもOKです)に、これを子どもに提示して、全員でルールを共有しておくといいですよ。
学習規律を“徹底”するってどういうこと?丨学習規律定着の方法📕

徹底するというのは、「提示した学習規律に合わない行動を子どもがとったとき、やり直させたりしてそのままにしないこと」です。
これは指示の出し方についての記事でも似たようなことをお話しました。
指示の出し方についての内容も、学習規律と大きく関係します。
こちらも必ず読んでほしい記事です!

例えば、先程紹介した<授業中の約束>に当てはめて考えた場合、
「手を挙げて当たった人だけが発表します」というルールを提示したのに、手を挙げていないのに「◯◯だと思う」とか独り言のように言う子ども(必ずいます)を担任は当ててはいけません。発言を拾ってもいけません。
どんなに良い発言だったとしても、です。
当てた瞬間、他の子どもは
とズルズルとルールが崩壊していってしまうのです。
もっと詳しく
●机の上や中は必要なものだけ!
⇨机の上については授業の最初に、必要のないものが出ていないかチェックしましょう。また、例えばその日の授業で教科書を使わない場合には、教科書は片付けさせるようにするといいです(この辺は指示の出し方の記事でもお話しています)。
また、机の中については朝のしたくルールで何をどこに片付けるのか指示しています。最初の時期は、朝の会の前に指定した場所以外に物を片付けていないかチェックしましょう。さらに、帰りの会についての記事ではお道具箱を机の上に出して帰るよう指示しています。このとき、必要のないものは持って帰らせるようにします。
●筆箱の中身も必要なものだけ!
⇨こちらは、一週間に1回、どこかの授業のはじめに抜き打ちでチェックするといいです。
●手を上げるときには、何も言いません。当たってから「はい」と言います。
⇨「はい」と言いながら手を挙げた子どもを当ててはいけません。「しー…」と合図をして、その子が気づいてから他の子どもを当てるようにします。
●反応は同じときには「同じです」、そうじゃないときには「わかりました」と言います。
⇨違うことを言う子どもがいたら、やり直しさせます。
●友達が傷つくような言葉は使いません。
⇨少しでも傷つくような言葉を言ったときには、容赦なく叱ります。
●お話は最後まで聞きます。話の途中で口は出しません。友達が発表するときも同じです。
⇨話の途中で口を出す子どもがいたら、話をストップし、じー…っと子どもを見ます。そしてその子どもがハッと気づいたら話を続けます。友達が発表するときも同じように、ストップさせて気づかせます。
●一生懸命発表しているので、一生懸命聞きます。
⇨一生懸命聞いていない人がいたら話をストップし、じー…っと子どもを見て、気づいたら話を続けます。
●授業中は、立ち回りません。質問がある場合も同じです。自分の席で、手を挙げて待ちます。
⇨やり直しをさせます。「今回は仕方ない」と質問を受け付けることは絶対にしません。子どもは、毎回「今回は仕方ない」と思ってもらえるのではないかと考えます。
いつからいつまで“徹底”するといいの?
以前、4月の子どもが学校に来だしてからの最初の一週間は、その中でも最も子どものルール等の定着がしやすい時期だとお話しました。
ですので、4月の最初から。そして、4月いっぱいは徹底して指導していきます。
「これくらいならいいか」と許していくと、「前は許してくれたのに!」と子どもは反発します。担任の指示が通りにくくなる原因になります。ですので、とにかく厳しめに!
4月の最初の時期は、子どもは基本的に「良い子」だと感じます。
でも、それは最初の時期だけです。この状態を保つには、技術が必要です。
「そこまで厳しくしなくてもいいんじゃないか?」と思うかもしれませんが、注意しましょう!

wordデータはこちら
\wordデータです。クリックでダウンロード!好きなサイズに印刷して使ってください/