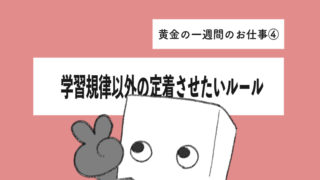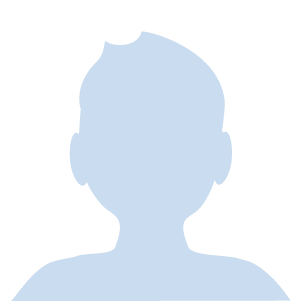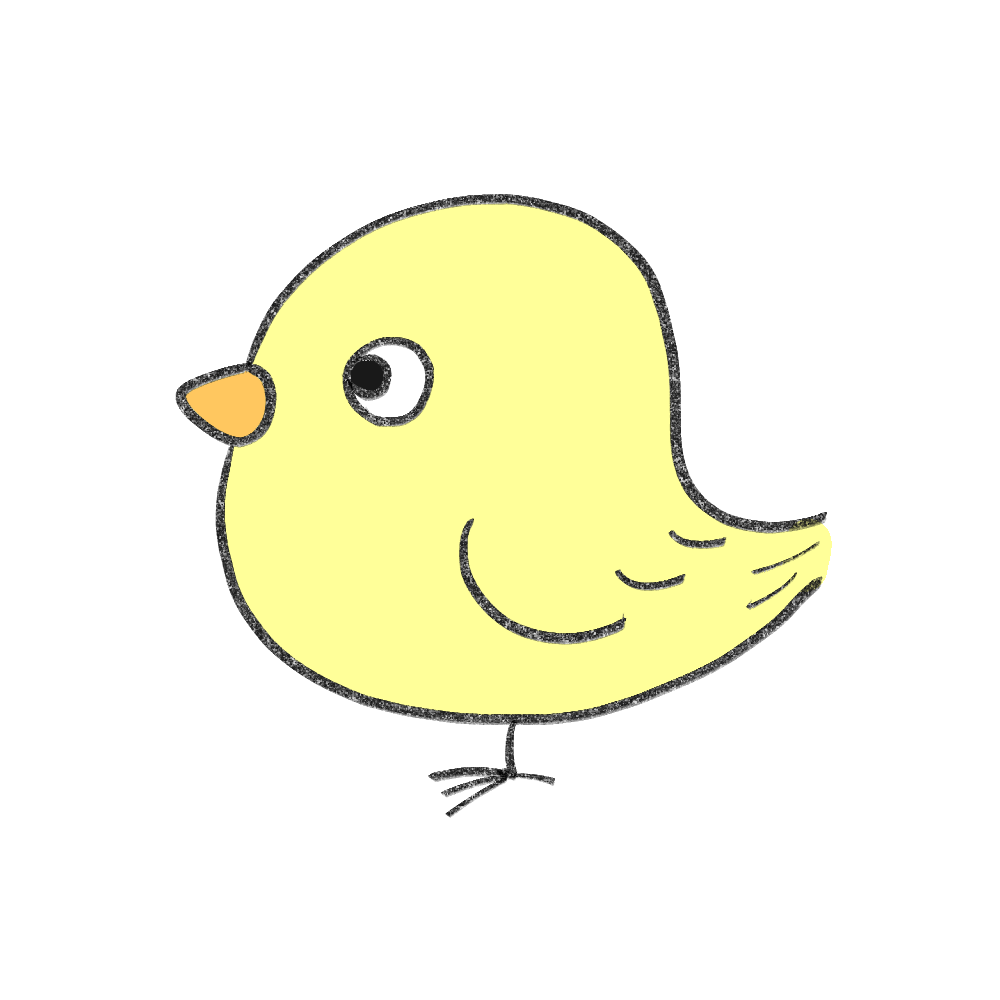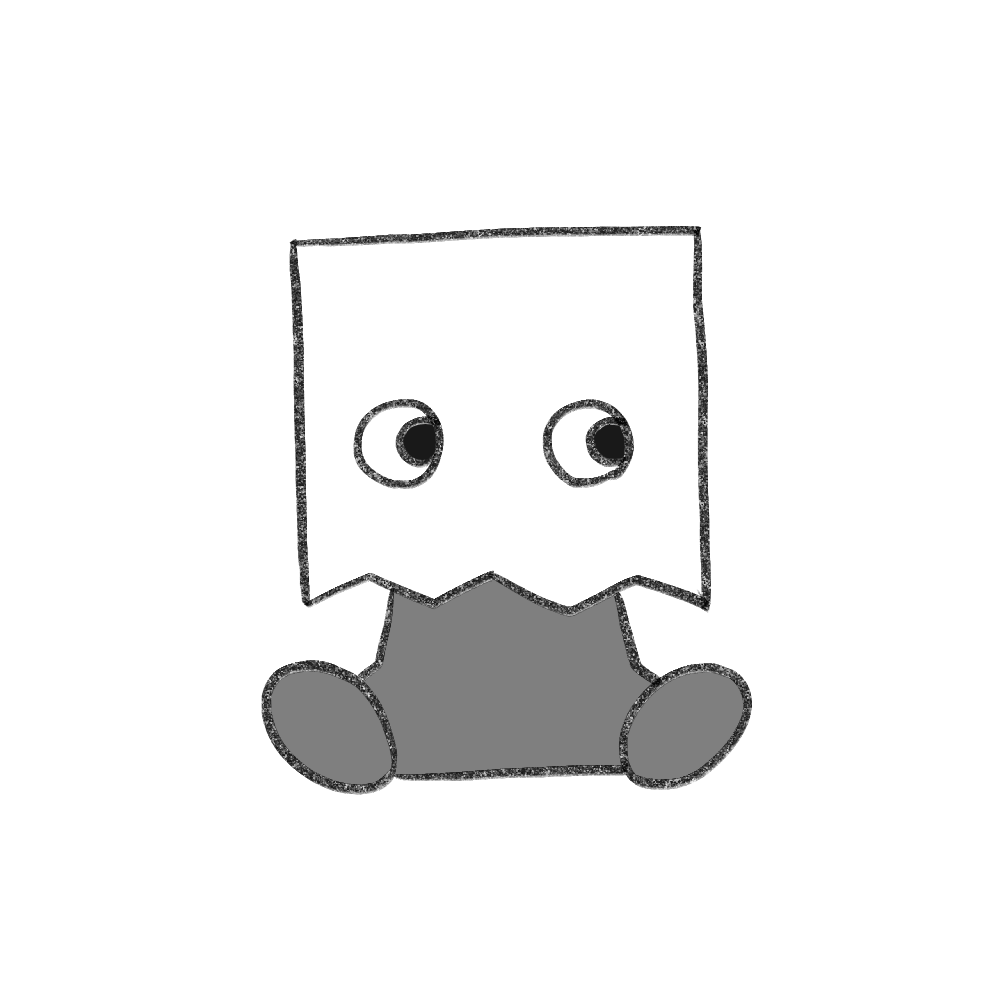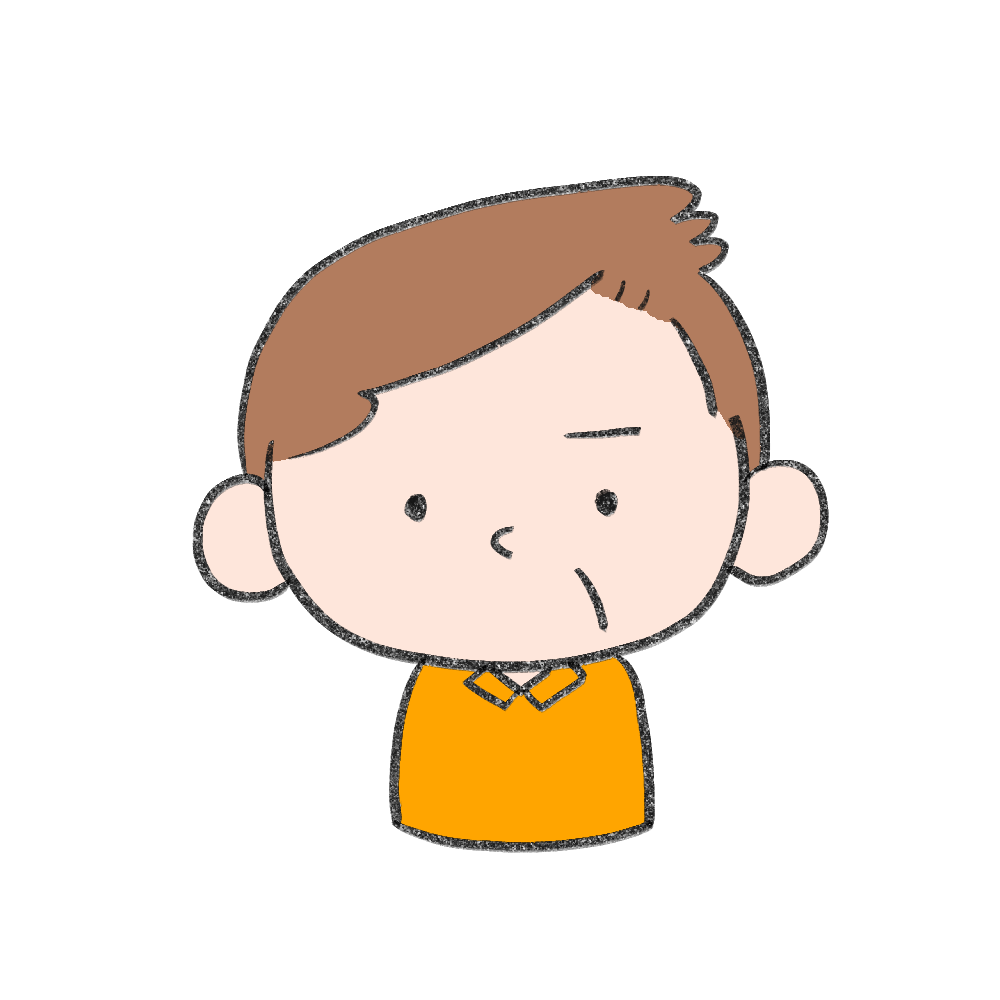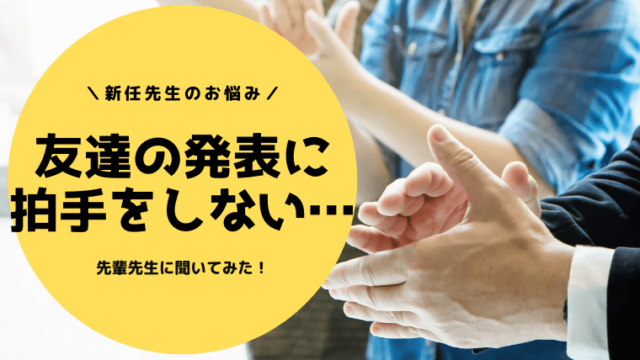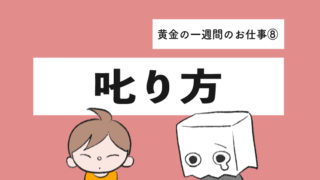\黄金の一週間⑥はこちら/
https://hiyokkonote.com/calssgame/
Contents
絶対に知っていてほしい、線引をはっきりさせることの大切さ📕
子どもへの指導で大切なこと、それは線引をはっきりとさせることです。

少し、私の失敗談をお話します。
遅刻した子どもへの対応についてのお話です。マンガにも描いていますが、もう少し細かくお話します。
私は、最初授業に遅刻した子どもを、理由によっては許していました。
例えば、「トイレで、お腹が痛くて」という理由での遅刻を許したとしましょう。
そしたら、「理由があれば遅刻していいんだ」とそれを理由に遅刻する子どもが出てきたんです。時間を守ろうとしていなかっただけなのに、
と、こんな感じで…。
そこで、私は子どもを叱りました。
“嘘”や“先生・友達を馬鹿にしたような行動”だと感じたからです。これって普通のことですよね。みなさんも「そういうときは叱ればいいじゃん」と思いませんか?
でも、その“嘘”や“先生・友達を馬鹿にしたような行動”で線引きをするのって、とても難しいんです。嘘だと見越して叱れば、
と不満を持ち始めます。
明らかに小馬鹿にしたような態度(べろべろばー等)だと、指導しやすいのですが、子どもって意外と賢くて、そんなことはしません。ギリギリのところを狙ってきます。
そんなこんなで、私は屁理屈の対応を、どうしたらいいのかがわからなくなりました。
そもそもなぜ“遅刻したら指導する”という線引にしなかったのか。
それは、自分が何かミスをしたときに理不尽に叱られるのが嫌という理由からでした。
「やっぱり理由は聞いてほしい」そう思いませんか?
だけど企業説明会や教員採用試験のときなんか、仕方なくても許されるかは別問題なんですよね。公の場(たくさんの人が関係している場)では、許されるわけではないこともあるんです。
授業は、企業説明会ほどではないかもしれませんが、公の場であり、そして学校は、そういう社会の厳しさも学ぶところです。
ですから、“遅刻したら指導する”という線引でいいんだと後になって思いました。
遅刻した子どもがいたら、ガミガミ叱らず、毅然と対応する(どうすべきかはっきりと、真剣さが伝わるように伝える)。理由は後で聞く。それでいいんです。変に優しくする必要はありません。
“遅刻したら指導する”の線引の方が、「遅刻はどんな理由でもだめ」になるのですから、子どもにとってわかりやすく、初任者教員は指導しやすいです。
“線引”をはっきりさせる大切さを知った上で、みなさんが指導法を考えることができるように、お話しました(^-^)
もちろん、“遅刻したら指導する”の線引にしなさい!と強制しているわけではないですよ。「自分が選んだ線引で、自分は指導できるのか」を考えるきっかけとなれば、うれしいです。
ベテラン教員が実際に行っている指導法
Twitterでベテラン教員の方々に質問をしました。
たくさんお返事をいただいたのですが、今回はその中でも“多くの初任者教員が実施しやすそうなもの”を基準に、私の方でいくつか取り上げて紹介させていただきます。
はじめに…多くのベテラン教員が話していたポイント
それは、教員も時間を守ることです。
授業開始の時間、守ります。万が一遅れた場合には、待っていた子どもに謝罪、感謝の言葉を述べるようにします。そして、忘れがちですが、授業の終わりの時間も守るようにしましょう!
①A先生の場合
教員は、チャイムの1分前に黒板の前に立って授業の雰囲気を作る
②B先生の場合
- チャイムが鳴ったら、指導者の価値観を明確にするために、まず座っている子どもを褒める
⇨時間を守ることの良さを価値付ける - その後、離席している子どもには
「チャイムが鳴っています」…状況の確認をして
「自分の席に座りなさい」…明確な指示を出す
と、毅然と指導する(ガミガミ叱る必要はありません。きっぱりと話します) - 離席していた子どもについては、授業終了後に指導する。理由を尋ねる。
③C先生の場合
- チャイムが鳴ったら時計を見て座っていた子どもを褒める
- そのやりとりを見て座れた子どもには、「周りを見て気づけたね」と褒める
⇨「開始時間には座れることが大事」なのを共有するため。気づけた、座れた行動を価値づける - 気づかない子どもには、「あと3人!どうすればいいかな?」と周りを見て気付けるように声かけをする
- 全員が座った後、改めて何が大切かをはっきりと伝える
・授業は一人ひとりの大切な時間であること
・自分とみんなのためにけじめをつけることが大切であること
④D先生の場合
- 授業開きのときに、思いを伝える
「私は終わりのチャイムを守ります。皆さんは始まりのチャイムを守ってください。私は45分間の授業を計画しています。皆さんにわかるように教えるために45分間必要です。ご協力よろしく」 - あとは、チャイムが鳴ったら授業をはじめるようにする。待たない。挨拶もしない。
その代わり、遅れたら損と思わせるような授業をする!
(例えば、チャイムが鳴ったらフラッシュカードをするとか、3分程度。5分以内には終わらせる)
トイレや喧嘩で遅れた子どもが出てきた時は…
- 『授業はみんなの時間です。あなたの理由でそれを奪ってはいけない。気持ちはわかるけれど、チャイムの前にはとりあえず教室に来て座りなさい』とはっきり伝える
忘れ物をした子どもへの対応について
授業の忘れ物の場合
こちらは、私が初任者教員の頃、ベテラン教員に教えてもらった方法です(^-^)
- 授業の忘れ物は、授業がはじまる前に先生に報告します
- 授業の忘れ物をしたときは、連絡帳に赤色で「◯わ 忘れた物の名前」を書き、先生に見せに来ます。連絡帳を先生が預かっている場合は、取りに来て書いて、先生に見せます(先生は、印鑑を押す)
こちらのルールを子どもに予め伝えておき、徹底しましょう!
徹底するというのは、例外なく守らせるということです。
宿題忘れの場合
宿題忘れについては、こちらの記事にまとめています(帰りの会シート【漫画】のところにある、“注意”という枠の中です。)↓
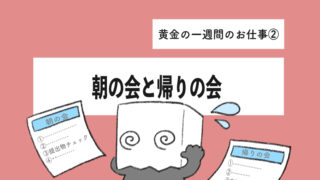
その他の徹底するといいルール
徹底するといいルールは、他にもあります!
まだ読んでいない人は、ぜひ読んでください(^-^)