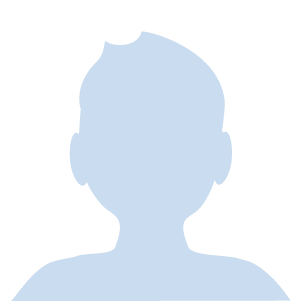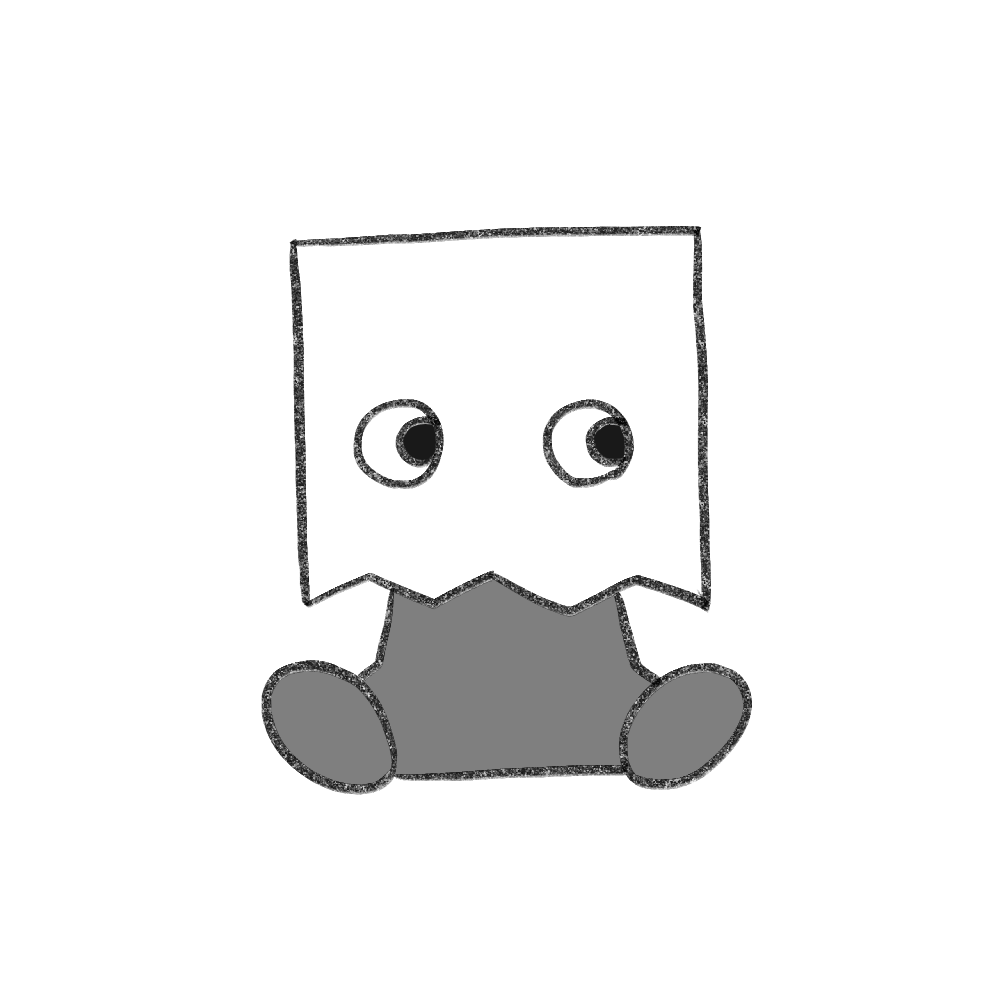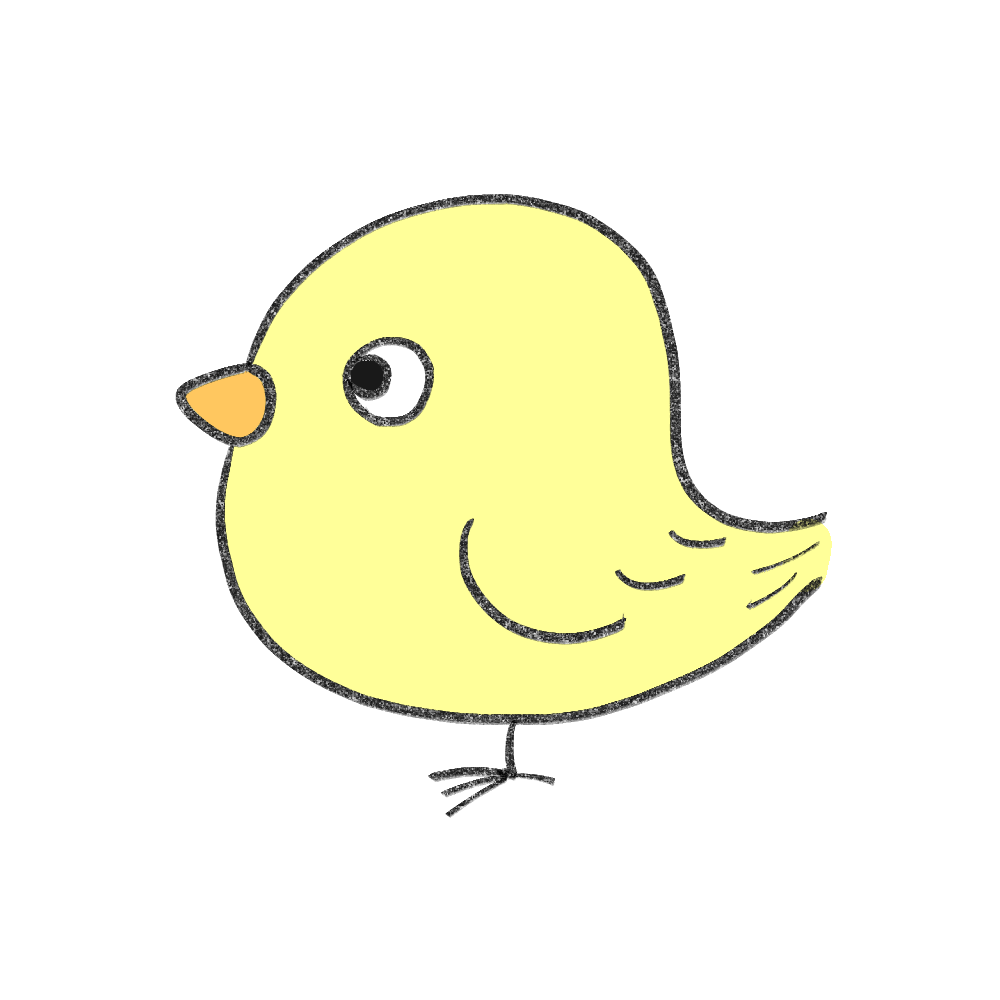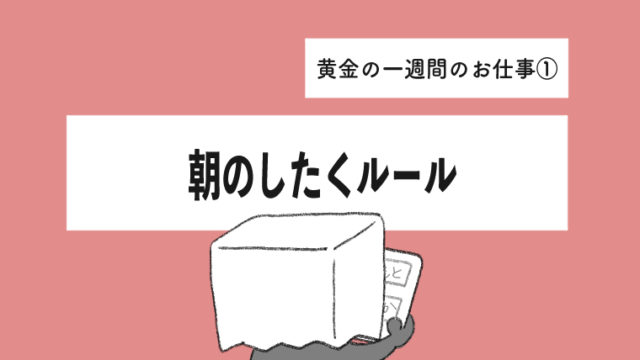\始業式当日のお仕事③はこちら/

絶対に知っていてほしい、教員と子どもの間の距離感📕
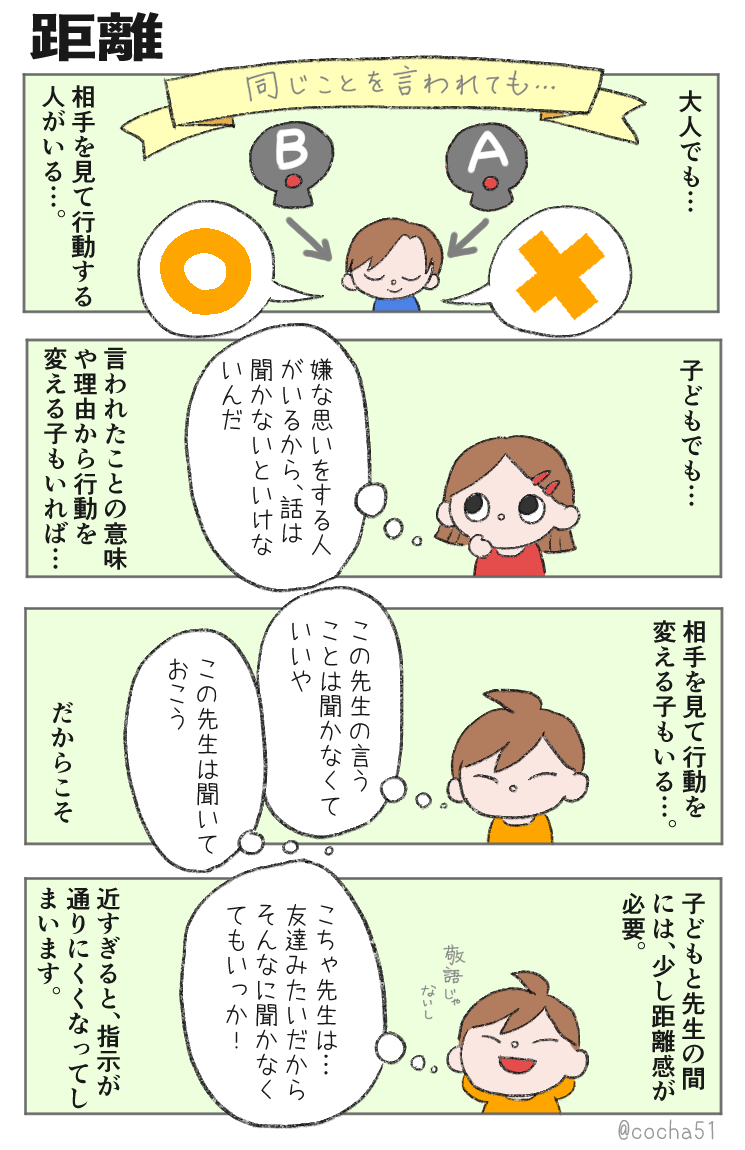
子どもと教員との間には、少し距離が必要です。
一定の距離がないと、子どもは先生を友だちのように感じてしまい、指示が通りにくくなってしまいます。
なんて思われていまします。
つまり、先生は子どもに「この先生の言うことは聞かなくちゃ」と思ってもらえる立場をキープする必要があるということです。
そのために、最低でも授業中は、お互い敬語を使うようにします。
もし、敬語を使わない子どもがいたら、
やり直しをさせます。
やり直しをさせることで、「守らないといけないこと」と学びます。
やってはいけない対応
という感じで流してはいけません。
流す=許すにつながってしまうと考えた方がいいです。
子どもの机とイス決めで必要な準備
当日必要な準備はこちら↓↓↓
- 教室内で机とイスを低め・普通・高めに分けておくこと
- 名前シール…1人2枚ずつ(イスと机用)
※個人的にはビニールテープで作るのがオススメです。
名前シールをビニールテープで作ることをオススメする理由
始業式当日の机決めでは対応しきれなかった子どもの机やイスは、
また時間のあるときに対応していきます。
全ての机やイスが調整しやすければよいのですが、実際は錆びているものがあったりとうまくいきません。これがまた固くて本当に大変なんです…。
そういうときに、名前シールを張り替えられる環境だと、イスを交換して調整することができるようになるので、楽になります。
名前シールを貼るところまではしてほしい!
名前シールがないと、こんなことが起こります↓

大人だと「そうなの。私はどっちでもいいよ。○○くんこっちのイス使っていいよ」なんて会話が出てきたりしますが、子どもはそうはいかないこともしばしば…。
突然イスを持って○○へ集合するようにと言われたこともあったので、学校が始まって2日目くらいまでには名前シールを貼っておくことをオススメします。
机決めのやり方📕

注意点①と注意点②は、前回の記事の「絶対に知っていてほしい、先生が言ったことは絶対に守らせるということの大切さ📕」に理由を書いています。
出した指示は必ず守らせるようにしましょう!

おおまかな流れは、マンガの通りです(^-^)
絶対にやってはいけない対応
机や椅子の高さが合わない子どもがいないかチェックする時、たくさんの子どもが手を挙げるかもしれません。
先生から見ても合わないなと感じた人だけ、変えるようにします。
また、
と指示をしたとき、
…なんていう子がいるかもしれません。このとき、
…という対応はとってはいけません。
と学んでしまうからです。学習って怖いですね。
一号車とは
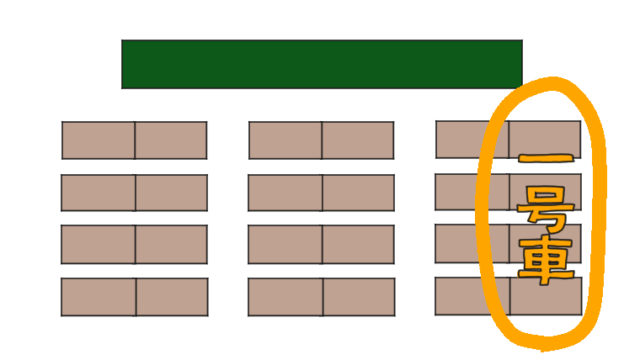
もし、1時間でできなさそうだったら…
2時間かけてもいいと思います。
ただ、授業時間は守るようにした方がいいです。
子どもに時間を守ってもらいたいのなら、教員も守っていきたいですね。
区切りの良いところで一旦中断し、休み時間に入りましょう。