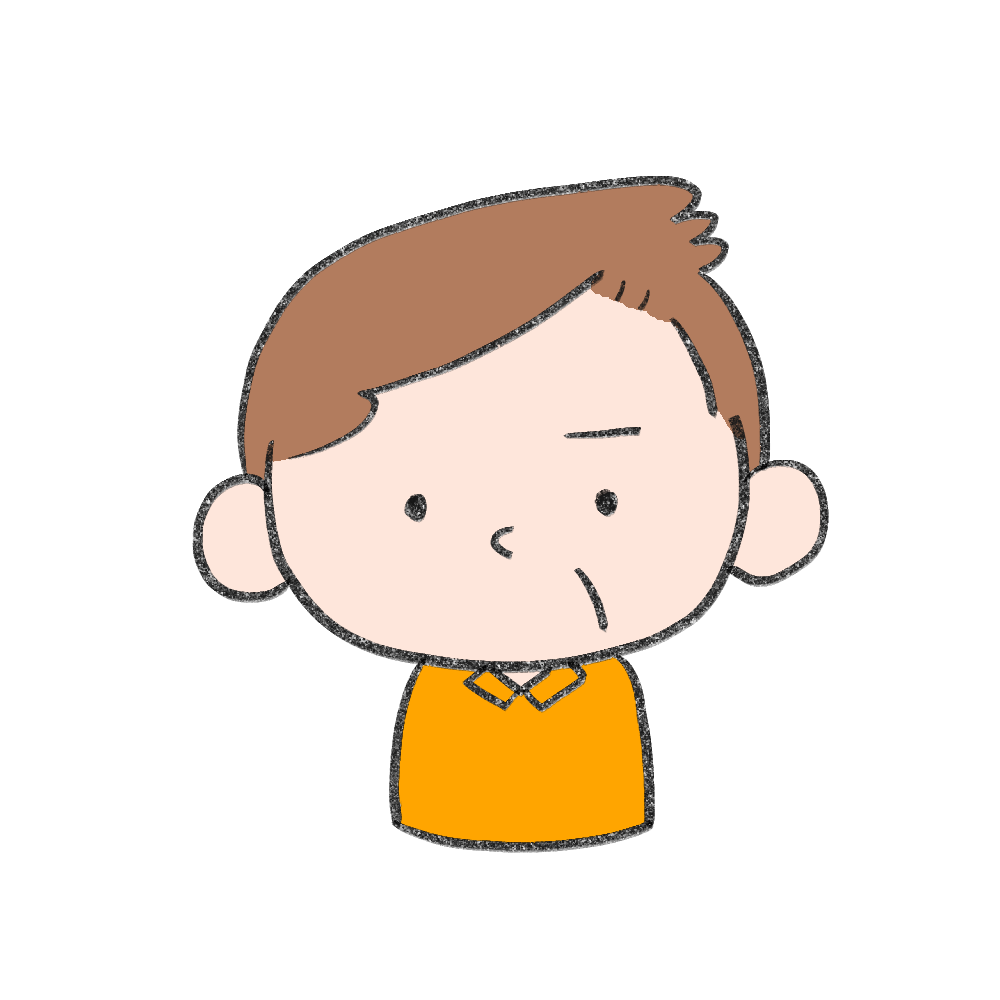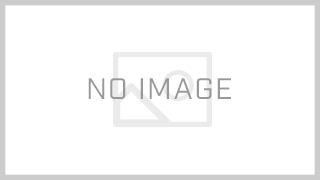こんにちは、こちゃです!
最近、「もっと初任者教員に寄り添って何かをしたい」と考え、【ひよっこカフェ】というZOOM会議を開いています。
<【ひよっこカフェ】とは?>
Twitterで不定期に開催している、主に初任者〜3年目まで教員を対象とした会。
私(司会)+先輩教員約4名で初任者〜3年目までの教員の悩みや質問に答えていく。
大体こんな感じで進んでいきます↓
- 事前に聞き手(初任者〜3年目までの教員)を募集する
- 事前に聞き手に「先輩教員に質問したいこと」を聞いておく
- ②を元に、私がひよっこカフェ当日の内容を組み立てる
- 当日、先輩教員に質問に答えていただく。
聞き手の人は先輩教員からのアドバイスを聞いて「ここをもっと知りたい」ということをチャットに書き込んでいく。(私と先輩教員は、そのチャットを見て質問を拾ったりします)
.
今日は、【第二回ひよっこカフェ】の内容を簡単にまとめていきます!
「当日参加できなかったよ…どうしよう」
「他の初任者〜3年目の先生って、どういうことに悩んでいるんだろう?」
「いろいろな事例を知っておきたいな」
という人は、参考にしてくださいね(^-^)
Contents
学級経営関係
質問①

既に時間が過ぎてしまっている学級では…
仕切り直しをすると良いですよ。学活を使って、ルール作りをします。
ルールは、先生が「こうなってほしいな」というものでOKです!
もし、罰を作るような雰囲気になってしまう場合、
と話し、「得(これを守ることによって、何を得られるのか)」の面に話を持っていきましょう!
友達の意見を聞かないときは…
例えば、Bくんが話を聞かない子どもだったとしますよ。
Aさんが発表している途中で、
と止めて、
とBくんに当てます。
Bくんはどきっとして、「〜だと思います」と言います。
そしたら、今度はAくんに
と尋ねます。
Aさんが「違います」と言っても、「違うんだね、でもBくんの考え方も面白いね。それでAさんは何て言おうとしたの?」と続けていくことができます。
Bくんはどきっとするでしょう(笑)
Bくんが何も言わなかったり、「聞いていませんでした」と言うときもあるから、そのときは違う対応が必要になるけどね。
もしくは、発表のタイミングでBくんに当てて、 そのとき他の子供に喋ってていいよと指示をします。 その状態でBくんには発表させます。
発表させたらお喋りを止めさせて、「どんな気持ちだった?」と聞きます。 すると、Bくんは自分の言うことを聞いてもらえない子の気持ちがわかるようになるので、少し落ち着くんじゃないかな。
チャイム着席については…
遅刻した子どもには、理由を聞きます。
…が、まずはきちんとチャイム着席していた子どもが損をしないようにしないといけません。
具体的には、遅刻した子どもには、話を聞きにいくまでの間、後ろに立って待っていてもらうようにします。
そして5分くらい授業を進めて、遅刻していない子どもに指示を出して、遅刻した子どもに話を聞きに行きます。
授業すぐに話を聞いてしまうと、チャイム着席していた子どもは「私たちはちゃんと時間を守っていたのに、なんで待たないといけないの?」ともやもやしてしまうからです。こういうところから、教師への不信感が出てきますから、注意しましょう。
理由が「わかるな〜」という子どもには
と言います。
一方、理由が「う〜ん…」という子どもには
という話をします。この話をした上で着席させます。
あと、チャイムと同時にジャンケンをするとか、ちょっとした楽しいことを時々入れるようにするといいですよ。ルールは「得」を感じさせるようにしていきます。
質問②


誰かが話しているときにお喋りをする子どもがいたら…
基本的に、誰かが話しているときにお喋りをする子どもがいたら、
- 話をストップさせて
- 気付いたら
- 続ける
というのを繰り返します。 ただ、なかなか改善しない子どもがいますよね。
こういう最後までお喋りをやめられず残っている子どもは、そういう特性の子供が多いです。
そういう子どもには、別の手立ても必要になってきます。
例えば、その子供に「絶対あなたから当てるからね」とこっそり約束をしておきます。
あとは、「言いたいことがあるの?最後に質問受け付けるからね。そのとき忘れないように覚えておいてね」と言って、話を続けるとかね。
こういう最後までお喋りをやめられず残っている子どもを叱り続けると、悪目立ちしてしまうことがあります。
そういう場合、例えば「他の人もしてるのになんで俺ばっかり!」と言われることがあります。
こういう場合は、「お喋りをやめたくない」ではなく「俺ばっかり注目されるのが嫌だ」というサインであることが多いんですよね。なので、放課後2人で話して、その子だけに伝わるサインをもっておくと良いです。
例えば、先生が手で優しく合図をしたら、それでお喋りをやめてね、とか。 つまり、「人前で注意される」のを緩めてやる(でも注意はしっかりしてる、みたいな状況をつくる)ってことです。
何より大切にしてほしいことは…
やっぱり頑張っている人を褒める!これが大切です!
褒め方は、「先生が望む行動をそのまま口にする」だけで良いです。例えば「目見てくれてるね」とか。
褒めるときは、全体より個人を褒めます。 なるべく、全員同じことで褒めるようにすると良いですよ。 「いつも目見てくれてるねー!」を全員分褒めるような感覚です(笑)。
そうすると「あ、こういう行動が良いのか」と子どもが認識しやすいんですね。 人を見て学ぶだけでなく、本人も褒められることでわかりやすいんです。
あとは、「目を見て話を聞いてくれました」とか、手紙を一筆、連絡帳に挟んであげると、家で褒められるので良いです。 連絡帳なので同じ内容でもいろいろな人に書けますよ。
他の先生と協力するのもあり
「○○先生が〜って褒めてたよ」と伝えるのもいいですね。
授業準備関係
質問③

社会の授業A
教科書を読んで→「自分たちの県はどうかな」といったように進めていくとわかりやすいのではないでしょうか。教科書の表はこうなってるけど、私たちの県の表はどうかな、と確かめていく感じです。
社会の授業B
教科書を「読み解く」のもいいです。
- 「Aさん、ここ読んで」と読ませていって
- 教科書の人物が何か図を見て喋っていたら「この人はどこのグラフを見てる?」「このグラフの下の横線は何を書いてる?」「縦線は何かな?」「このグラフから何がわかる?」といった感じで読みといていきます
社会の授業C
資料を最初に見せて、「そこから何がわかるかな?」と進めていくのもいいですね。
社会の授業D
先生用教科書の右下(?)にある、板書例を見て「これを出すにはどういう質問をしたらいいかな」と考えて授業を作っています。
社会の授業E
教科書通りに進めますが、教科書の資料を自分の県の資料に差し替えて進めるといいです。資料は自分の県だけど、教科書通りに進めたらいいのでやりやすいのではないでしょうか。
こちらの本がオススメだという話が出ました(^-^)↓
学年別になっているものもありました↓
.
国語の授業についても聞きました
国語の授業は、先輩教員4名一致してこちらの本がオススメだそうです!↓
.
授業指導関係
質問④

方法A
教科書の問題を解かせる際、 例えば①〜⑥まで問題があったら、①、③、⑥だけ問題を解かせるようにします(これは、なるべく違う傾向の問題を選ぶようにします!)。
タイマーで測り、時間がきたらすぐ答え合わせ。このとき、早く終わった人は②と④を解き、それも終わったら教科書の後ろに問題が載っているので、そこを解くよう指示をしていました。
最悪、そういうできる子は塾の問題集とかドリルをもっている場合があるので、持ってきてやっていいよと言ってもいいのではないでしょうか。
方法B
難しい問題を3つ準備しておきます。応用と難問です。
「応用応用難問」か、「応用難問難問」か等はそのクラスの実態に合わせて!
3レベル準備しておき、一番難しいものは中学受験の問題にしたりします。ちなみに、単元と関係ないひらめき問題をもってくることもあります。そうすると、普通の問題より難しく、時間もかかるので結構いい感じになりますよ。
方法C
できた子どもにはヒントカードを書かせて→書いたら黒板に貼らせて→わからない子供がヒントカードをとって、解く(そのヒントカードはノートに貼らせる)ようにしていました。
方法D
早く終わった子どもには練習問題を作らせるようにします。
練習問題は、
- 苦手な子どもでも解けるような問題
- 得意な子どもが「うーん」と思うような問題
とか、ある程度指定していました。
これを回収して、活用することもできますよね。
方法E
- 困っている子がわかるような解説を書いてね
- 習っていない子にもわかるよう解説を書いてね
と指示を出します。
授業の最後にポイントとして発表させると、早くできた子どもも嬉しくなって取り組みますよ。ちなみに、学級通信なんかに載せるのもいいですよね。
その他
質問⑤

これはもう、周りに頼るしかないですね…。
いきなり40人は子ども的にも難しいだろうから、放課後に残って教科指導ができたら、そのとき1人一緒に誰かと残ってもらって…って、まずは友達1人と一緒に過ごすところからがいいかもしれないですね。そうして慣れさせていく感じ…。
先生も1人で抱え込み過ぎないようにしてくださいね!
質問⑥

対女子の場合は…
レディとして接します!
高学年になると、個別に話をするのも全体の前で話をするのも嫌がる子が出てきます。そういうときは、間接的に褒めていくのが良いです。
Aさんを褒めたいけど、Aさんと仲の良いBさんに「Aさん、これよかったよね」と伝えるなど。 漫画が好きなら漫画の話で近づくとかしないと難しいですね…。
あとは、すごいなと思われるポイントを持つことも大切です。
男子の場合は…
女性の先生の場合、男子が先生をなめて…といいますか、軽く見て指導が難しくなることがあります。
そういうとき、周りのオラオラ系の先生が来て指導するといい子になったりして、「何だよー!」と思うことがあると思います。
だけど、周りの先生がオラオラ系で、そのやり方があなたに合わなかったら、それはあなたに合うやり方を極めた方がいいです。それが個性になりますし、後々学年として役に立つことがあります!
オラオラ系ジャなくて僧侶になってもいいじゃない!
「この人のやり方ならやっていけるかも」という先輩を見つけて、真似をしていきましょう!
質問⑦

転入生への対応A
ガムテープに名前を書かせて、それを使ってかくれんぼをすると楽しいですよ。
転入生のガムテープを見つけると10ポイントとか、転入生のだけ小さいガムテープにするとかして、その子に隠させます。
すると、全員で転入生のテープを一生懸命探します(笑)
転入生への対応B
安心してもらえる環境づくりが一番かなと思います。
例えば、趣味が一緒の子を見つけることができるきっかけを作るとか。それだけでも違いますよ。
転入生への対応C
時間があるのなら、事前にその子に何をしたいかみんなで考えるのがいいかな。
先生がやりすぎるより、子どもにしてもらうのが一番安心するだろうからね。