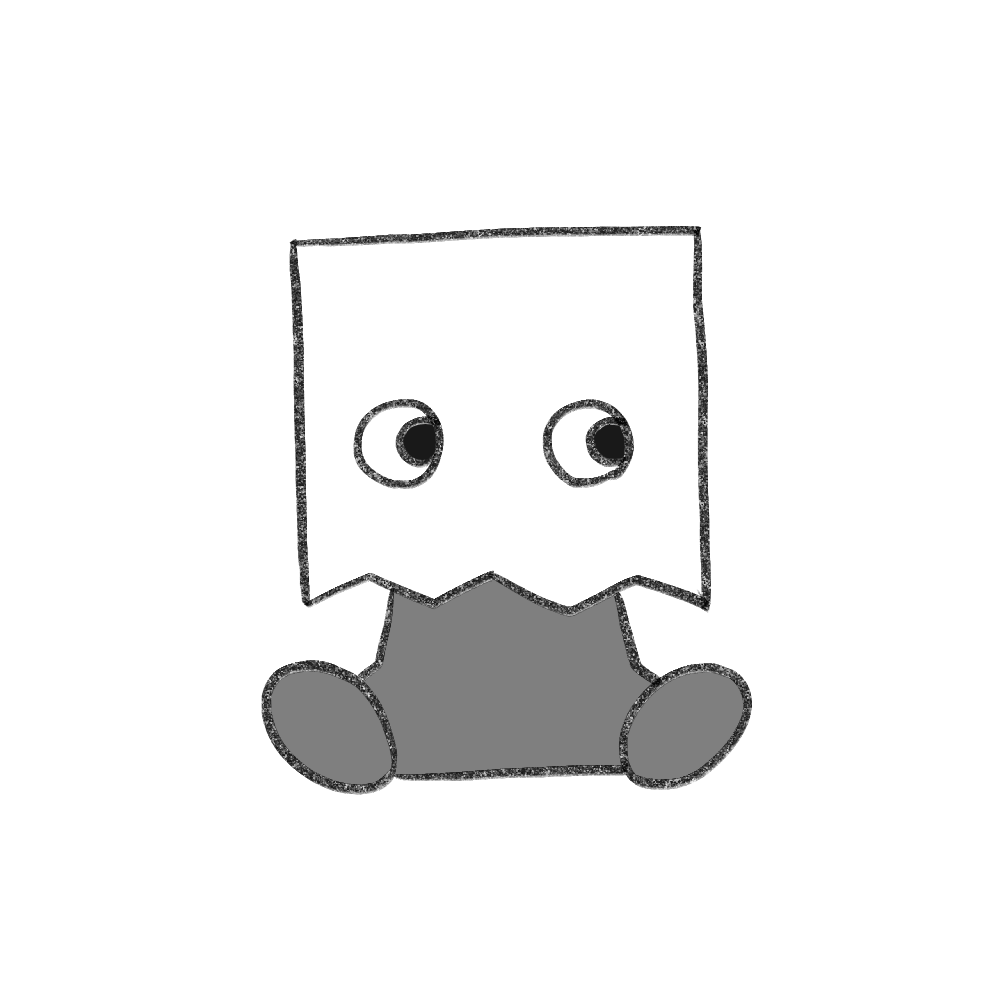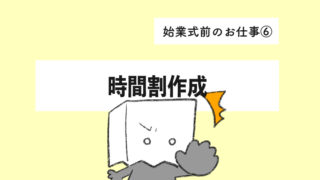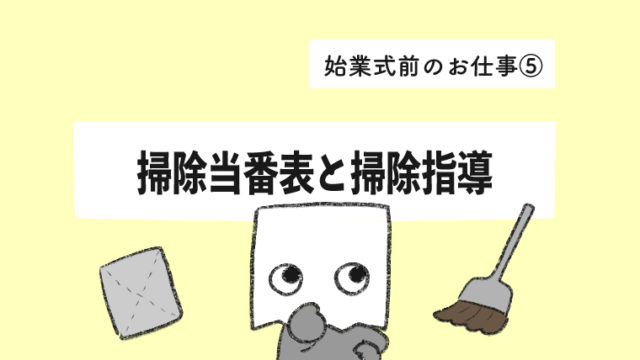
\始業式前のお仕事④はこちら/
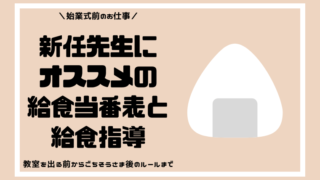
Contents
ベテラン教員に教えてもらった、掃除の取り組み方を左右させるポイント📕

今回は、Twitterでベテラン教員のみなさんに掃除指導について質問しました。
返ってきたコメントを読んでいると、掃除の取り組み方にはいくつかポイントがあることがわかりました。それがこちらです。↓
<掃除の取り組み方を左右させるポイント>
- 人数配置
⇨人数は必要最低限に抑え、暇ができないようにする - 役割分担
⇨誰がどこを掃除するのかを明確にする - 掃除の仕方を事前に教えておく!
- 支援が必要な子どもへの配慮
⇨例:机棚拭きをさせる
個人的に驚いたのが、掃除の仕方を事前に教えておくということ(事前指導)でした。
ちなみにこちらは、中学校のベテラン教員も教えているとお話ししていました。
初任者教員にオススメの掃除当番表
給食当番表同様、掃除当番表もこのような表がオススメです。↓

給食当番表ととても似ていますよね。だけど、掃除当番表は考えることが多くて、少し複雑です。これから作り方を説明します(^-^)
①自分の学級が担当する掃除場所を確認し、掃除場所別に色を決めておく

学校のビニールテープにある色がオススメだよ!
②各掃除場所の人数を決める
掃除場所はなるべく細分化して、多くても一箇所3人までとします。
教室等の広い場所も縦3つ4つに分けて、担当者に責任を持たせるようにするといいです。
\まずは細分化/

\次に振り分け!多くても一箇所に3人までだから…/

\確認/

\完成!/

③道具の数を確認する
- 自分の学級の掃除道具に、ほうきやモップ、ちりとりがそれぞれいくつあるのか
- 自分の教室以外の場所に掃除道具がある場合も、どんな道具がそれぞれいくつあるのか
を確認しておきます

④掃除道具を分け、足りない掃除道具をもらう

⑤それぞれの掃除道具に、②で決めた場所の色シールを貼る
\こんな感じ!わかるかな?/

掃除道具入れの中の網とほうきをかけるための長いS字フックは、100均で買う

網があることで、子どもが片付けやすくなり、掃除道具が荒れるのを防ぐことができます。
掃除道具入れの中って、フックがすごく高いところにあってかけにくいことがあるんですよね…。せっかくほうきがかかっても、S字フックが短すぎて揺れて、隣のほうきが落ちたり…もやもやポイント満載の場所です。
面倒くさがりな子どもはこういうところで、「もういいや!ポイッ!」…となってしまいます。
⑥④を元に掃除当番表を作る
\上から順番に振り分けていくだけ/

\完成!/

⑦掃除道具入れの中の写真を撮り、扉の内側に貼っておく
これがあるだけで整い方が全然違います!貼ることをオススメします(^-^)
はじめての掃除がある日には、掃除指導をしよう!
事前指導で教えること
事前指導は、実際の掃除の前に1時間とって行います。
- 道具の使い方
⇨箒の使い方(目線は箒の方を見る。床と擦るように、決してまだらにはかない。一列ずつ、全ての床をはく) - 導線
⇨箒をはく方向、雑巾がけの順番、ゴミを集める場所 - 手順
⇨教室の場合…
(1)机や椅子は、教室の前側に移動させる
(2)箒担当者が、教室の後ろ側から前にはく

(3)雑巾担当者が後ろから順にふく


(4)ふいたところから机・椅子を教室後ろ側に下げる

(5)教室の前側を箒ではき、その後に雑巾でふく
(6)机を横そろえて並べ、椅子を下ろす - 片付け方
指導の最後に「今日は、教室を一緒に掃除します。明日は、○○です。1日に一箇所ずつ先生が行きます。今日はわからないことがあるかもしれないけれど、自分で考えてゴミを無くしてください」と話しておきます。
掃除の時間の指導
先生は1日に1つの場所に着いて指導していきます。
掃除場所へ行って、掃除の最初から最後までを見て、必要なら指導をしていきます。
雑巾の絞り方やほうきのはき方がわからない子どももいるので、チェックします(^-^)
教員も一生懸命掃除に取り組もう!
子どもは、教員の様子を見ています。教員が一生懸命取り組むと、「掃除はこうやって取り組むものなんだ」と大体の子は真面目に取り組みます。
掃除中に掃除していない子どもがいたら?
掃除中に掃除していない子どもがいたら、「はいて」「ふいて」と声をかけて一緒に掃除します。